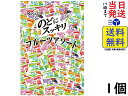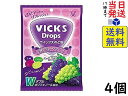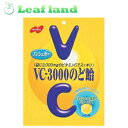風邪の引きはじめやのどの違和感があると、頼りたくなるのがのど飴ではないでしょうか?
他にも、ボイスケアをしたい時にも頼っているという方もいるでしょう。
のど飴と言っても、ただの飴にしか見えませんが本当に効果はあるのでしょうか?
効果がないとなれば買う事も無くなってしまいますが…
のどの痛みを和らげてくれる便利なアイテムなんですよ!
という事で今回は、以下の点についてお伝えしていきたいと思います。
- のど飴の効果について
- のど飴の選び方
- おすすめののど飴
- のど飴の正しい食べ方
- のど飴の注意点
のど飴について徹底解説させていただきますので、最後までご覧ください。
のど飴って効果ないの?あるの?

気になるのど飴の効果はあるのか?ないのか?についてですが…
結論から申し上げますと、のどに潤いを与えたり、のどの痛みを抑えてくれるといった効果があると言われています。
でもどうしてのど飴が、のどのイガイガに有効なのか見ていきましょう。
のどが痛む原因というのは、風邪などのウイルスで起こった炎症や、のどを使いすぎてしまった時に起こる炎症が原因と言われています。
炎症が起こる前に自然と治す力があるのですが、免疫力の低下・疲れといった事で炎症を抑える事が出来ない場合もあります。
そのせいで、のどが痛くなってしまったり、咳が出始めるといった症状が現れるのです。
これらの症状を和らげるには、粘膜を潤してあげる事が必要となってきます。
飴は、砂糖から出来ています。
砂糖というのは、粘膜を潤してくれるのに非常に役立つ食材なのです。
唾液の分泌量が増える事で潤いを与えてくれて、なおかつウイルスの侵入も防いでくれる役割を果たしてくれます。
また、のどを保湿してくれる役割もあるのです。
のど飴には、殺菌作用・洗浄効果というものがあります。(医薬品には、殺菌作用・洗浄効果に咳止めの成分がプラスされます。)
のどの炎症を治すには、ゆっくりと休む・カロリーの摂取というものが必要となってきます。
糖質にはカロリーの摂取を助けてくれる働きもありますので、回復する際に必要なエネルギーの確保にも役立ってくれるのです。
薬をなるべく使いたくないという方もいるでしょう。
特に妊婦さんなどに関しては、やはりお腹の子の為にも薬を飲みたくない方が多いです。
ですが、医薬品に属してしまうのど飴もありますので、口にする際は、必ず主治医に聞いてからにしてください。
他にも、カモミール・殺菌作用がある成分も含まれているのど飴もあります。
神経質な方の場合は、あまりおすすめ出来ないですがリスクはあまり無いと言われています。
それでも気になるという方は、薬剤師の方や婦人科の先生などに相談する事をおすすめします。
そもそものど飴って?
そもそも、のど飴には定義というものはありません。
砂糖・水あめなどでコーティングされており、有効成分が含まれているのが一般的とされています。
さらに、のど飴というのは3つの種類があるというのをご存知でしょうか?
- 医薬品
- 医薬部外品
- 食品
といったこの3つの種類があるのです。
よく聞く言葉ではありますが、効果・成分・味はそれぞれ異なりますし、ドラックストアでしか買えないといった物もあるのです。
有効成分によって効果が高いと言われているドロップ剤の事を意味します。
咳・痰・のどの痛みといった症状に効果があると言われている成分が含まれていて、製造・販売するには国の承認が必要になってくるのものです。
薬局やドラックストアのみの購入となりますが、最近ではドラックストアも増えてきているので、簡単に手に入れる事が可能となります。
市販薬と同じ扱いになってしまうので、効果は高いと言えます。
ただ、副作用のリスクもありますので、服用する際は注意が必要となります。
~医薬品ののど飴~
- 浅田飴(第2類医薬品)
- ルルメディカルドロップ(第2類医薬品)
- 南天のど飴(第3類医薬品)
- ぺラックスイート(第3類医薬品)
医薬品を基準にした有効成分が配合されているのが、医薬部外品というものです。
効き目も医薬品と違って、緩やかなドロップ剤となります。
製造する際は、国の承認は必要です。(販売に関しては、国の承認は不必要)
医薬部外品は、ドラックストア以外にも、コンビニ・スーパー・通販でも買う事が可能となっています。
医薬部外品というのは、どちらかというと症状を改善するといった目的よりも、予防を目的としているものです。
そのため、医薬品に比べて効き目は緩やかとなっています。
ですが、医薬品と比べると副作用というものはほとんどありませんので、医薬品よりも安心です。
副作用が少ないという事と、手軽に買えるといったメリットが医薬部外品にはあります。
~医薬部外品ののど飴~
- ヴィックス
- ルルのど飴
- DHC薬用のど飴 など
医薬品・医薬部外品とは違い、食品には有効成分が含まれていません。
つまり、効能・効果は認められないお菓子(飴)というわけです。
企業側が「これはのど飴です!」というものが、該当するという事です。
のど飴のパッケージによく書かれている、はちみつやハーブといったのどに良いと言われている成分が含まれている物が多いです。
のど飴として販売している物は、ビタミンCなどの栄養素を意識している物が多いため、鼻の通りなども良くしてくれる物が多いのです。
ただ、医薬品・医薬部外品ののど飴にあるような効果は無いと思ってくださいね。
味や食感はいろいろとありますので、そこがメリットの1つと言えるでしょう。
のどの乾燥を予防したい・気分転換したいという方におすすめかもしれません。
医薬品・医薬部外品とは違って、一般的な飴と同じくらいの値段で買う事が出来ます。
~食品ののど飴~
- 龍角散
- はちみつきんかんのど飴
- VC3000のど飴
- プロポリス など
医薬品・医薬部外品に関しましては、甘い飴ですのでたくさん口にしたいという方もいるでしょう。
ですが、成分の濃度や糖分の問題がありますので、たくさん口にする事はやめておきましょう。
1時間以内に3個までと書かれている商品もありますので、それらを守って舐めるようにしてください。
ちなみに、食品のところに龍角散と書きましたが、医薬品のイメージが強いという印象があります。
実は、龍角散には【医薬品】として販売している物もあります。
それは、粉末状の物や顆粒の薬、トローチといった商品が医薬品として販売されています。
飴タイプの龍角散に関しましては、医薬品に使われている成分は含まれておりませんので、気をつけてください。
のど飴の選び方

次にのど飴の選び方についてご紹介します。
ポイントを簡単にまとめますと、以下のようになります。
- 効果・成分・目的
- 薬用の種類
- 味・原材料
- カロリー
- 使い勝手
- 粒のサイズ
これらのポイントについて解説していきます。
※先ほどと重複する点がありますが、ご了承ください。
効果や成分、目的に合った物を選ぶのもポイントの1つとなります。
効き目を重視するのであれば、医薬品タイプの物を。
手軽に症状を抑えたいなら、医薬部外品タイプの物を。
美味しくのどをケアしたい場合は、食品の物を選ぶといいでしょう。
のどが痛かったり、腫れがひどいという場合は医薬品タイプののど飴を選ぶようにしましょう。
医薬品タイプののど飴には、有効成分が配合されており、効果・効能が認められています。
痛みや腫れ以外にも、咳・痰といった症状にも対応していますのでおすすめですよ。
もし、他の薬を服用している時は、主治医の方や薬剤師の方に相談してから舐めるようにしましょう。
症状を手軽に抑えたいという方は、医薬部外品ののど飴がピッタリ!
副作用も少ないので、安心して飲む事が出来ます。
ただ先ほども言いましたが、医薬品よりも効果は緩やかという事をお忘れなく。
医薬部外品には、口腔内の殺菌・のどの腫れ・痛みを抑えてくれる働きがあります。
美味しくのどをケアしたい場合は、食品タイプの物を選びましょう。
スーパーのお菓子コーナーで販売されている物と思ってください。
こちらも先ほどお伝えしたように、効果や効能は認められていない物となります。
あまり効果を期待しない方がいいですが、鼻の通りを良くしたり・のどを潤してくれるアイテムを選びたいのなら食品タイプののど飴もおすすめですよ!
食品タイプだと種類も多いので、自分好みの物が見つかるかもしれませんよ。
医薬品・医薬部外品・食品タイプののど飴でも、のどにとって悪影響を与えるものではありません。
ですので、のどに起きている症状や解消したい事がどのような事なのかを念頭に置いて、のど飴の種類を選ぶといいでしょう。
のどのイガイガを解消したいという場合は、医薬品でも医薬部外品でも食品タイプののど飴でも解消する事は出来ます。
咳やのどの痛みを抑えたいというのであれば、医薬品か医薬部外品ののど飴を選ぶのがおすすめです。
医薬品は効果は強い、食品タイプに関しては、効果が認められていないとお伝えしております。
「食品タイプじゃ効果が無いから、医薬品ののど飴舐めておこう」といった、効果が強めののど飴ばかりを食べ過ぎるのはNGです。
想定外の副作用を発症してしまう可能性もあります。
ですので、自身の症状に合ったのど飴を選ぶように心がけましょう。
効果や成分なども大事ではありますが、のど飴の【味】というのも選ぶポイントの1つに入れておきましょう。
やはり直接口に入れるものなので、味も重要視しましょう。
効果が高いのど飴を選んだとしても、味が気に入らなければなかなか舐め続ける事も出来ませんよね…。
効果も得られるわけがないので、しっかりとパッケージなどに書かれている内容を見ておきましょう。
医薬品や医薬部外品ののど飴というのは、効果はあるものの苦み成分が使われている事が多いです。
ですので、苦みがあまり得意ではないという方は、甘いのど飴を選ぶようにしましょう。
パッケージなどを見てみると、原材料が書かれています。
原材料で選ぶのもおすすめですよ!
栄養価が高いのがいいという方は、【マヌカハニー・プロポリス】がおすすめ。
プロポリスが配合されている物は、ピリピリとした刺激を感じるのが特徴となっています。
また、プロポリスは栄養価が非常に高いと言われているのです。
一方のマヌカハニーですが、希少価値が高い・栄養価・美容効果も高いと言われているはちみつの仲間です。
甘さも濃厚なのですが、辛味が独特なはちみつです。
高い効果を求めるのであれば、【UMF】【MGO】の数値が高い物を選ぶようにしましょう。
※UMF・MGOは抗菌活性値を表すものとなります。
美容効果も求めたいという方は、【かりんエキス】がおすすめです。
かりんエキスが、のど飴の定番素材でもあり、美容効果も高いと言われています。
ビタミンCやβカロテン、ポリフェノールも豊富と言われており、健康にも効果的と言われている原材料なのです。
さらに嬉しい事に、香り高く、フルーティーな味わいなので味も美味しいといったメリットがあります。
かりん自体、栄養効果の高さが認められているフルーツで、商品名に【かりん】と書かれていなくても、含まれている商品は多く存在しています。
食べやすいのど飴を選びたいのであれば、かりんエキスがメインとして使われているのど飴を選ぶといいでしょう。
高い栄養効果を求めるのなら【生姜エキス】がおすすめ!
生姜エキスは、栄養価の高さが非常に優れているため、いろいろなのど飴に使われている原材料です。
さらには、健康を維持するための効果がある成分、ジンゲロール・ショウガオールも含まれています。
爽快感を得たいという方は、【ミント・ハッカ】がおすすめです。
ミントやハッカが苦手という方も多いですが、口の中をスッキリさせたい時や爽快感を得たいという方に向いており、栄養補給にもなる原材料となります。
ミントやハッカが苦手な方は、りんごやオレンジなどのフルーツ系のミントが使われている物もありますので、そちらを選ぶといいでしょう。
ちなみに、ペパーミントは口臭が気になる方にもおすすめの原材料となります。
健康維持に繋げたいという方は、【南天の実】が含まれている物を選びましょう。
南天というのは、下の画像のような赤い実の事です。

南天は、昔から縁起物として知られている実で、健康維持の効果があると言われているのです。
o-メチルドメスチシンという有効成分も含まれているので、栄養補給も可能。
ちなみに、o-メチルドメスチシンの働きとしましては、咳を抑えてくれたり、気道の炎症を抑える働きがあります。
健康維持したいという方にはおすすめですよ!
のど飴には糖分が含まれているのがほとんどです。
ですので、カロリーや虫歯などが気になるという方は、シュガーレスの物を選ぶといいでしょう。
パッケージをよく見てみると、シュガーレスやノンシュガー、シュガーフリーと書かれている物もありますので、よく見てみるといいでしょう。
のど飴は、1日に数個食べるという方もいるでしょう。
1日に数個食べるという事は、カロリーも高くなってしまうのは当然の事です。
ですので、カロリーから選ぶのもポイントの1つと言えます。
中には、低糖質タイプののど飴も販売されていますが、あまり種類は多くないので選択肢は狭くなるでしょう。
意外かもしれませんが、使い勝手のいい商品もポイントの1つで、のど飴のパッケージもチェックポイントとなるでしょう。
出掛ける際、持ち歩きたいという方や配りたいという方は個包装ののど飴がおすすめです。
手も汚れたりしませんし、カバンの中に入れても問題ありません。
飴同士がくっつかないといったメリットもあります。
まとめ買いして置いておきたいという方は、個包装の物を選びましょう。
すぐに食べたいという方は、チャック付きの物を選ぶといいですね。
保存しやすいチャック付きの物であれば、手がふさがっている時でも直接袋の中から取り出す事が可能です。
食べきりサイズ(25g前後)ののど飴も販売されていますので、頻繁にのど飴を食べないという方にとっても便利です。
おすすめののど飴

次におすすめののど飴をご紹介していきたいと思います。
風邪や感染症の予防にも役立つと言われている、エキナケアエキス(アメリカ原産)が配合されています。
エキナケアというのは、循環器系・リンパ系・呼吸器系の解毒薬として効果が認められているものとなります。
適切な量を摂取すれば問題はなく、感染症などの抵抗力を上げるといった効果も科学的に立証されている成分となっています。
エキナケア以外にも、バンランコン・リュガンニク・キキョウといった東洋ハーブも使用されています。
味はミント系で個包装にもなっているので、持ち運びも便利ですよ。
また、甘さも控え目で後味もすっきりしています。
メントールが強めではありますが、鼻やのどの通りをスッキリさせてくれて爽快な気分になる事間違いなしです!
ちなみにカロリーは、1粒あたり14kcalとなります。
見た事がある方もいれば、あまり見た事が無いという方もいるでしょう。
スーパーやコンビニ、ドラックストアなどで買う事が出来る、森下仁丹ののど甜茶飴。
ムズムズしている鼻・乾燥が気になるという方におすすめののど飴です。
強すぎないちょうどいい刺激のメントールが鼻を通り、厳選されたエキスがのどに潤いを与えてくれるのです。
厳選されたエキスは、【甜茶エキス】【甘茶エキス】【甘草エキス】【生姜エキス】の4種類で、製薬研究のノウハウを生かしてのど飴に適した素材を選んでいるのです。
また、こちらの飴は香りや刺激が持続するように工夫されています。
ユーカリ・ペパーミントといった香料を、独自で開発したカプセルで包んでから飴に練り込んでいるんですよ!
口に入れて舐め続けていれば、飴に練り込まれたカプセルが溶けだして香りと刺激が出てくるといった手間が加えられています。
嬉しい事にノンシュガータイプののど飴なので、後味もスッキリしています。
甜茶味のする飴ですが、この味が食べ飽きないといった声も多いのど飴となっています。
パッケージはチャック付きで、カロリーは1粒あたり4.2kcalです。
食品に分類される、ヴィックスののど飴プラスハーバルミントパウダー。
厳選された8種類のハーブエキスが加えられているだけではなく、ポリフェノールもたっぷり含まれているのど飴となっています。
口どけがほどよく、ひんやりと冷たいミントパウダーのおかげで、のどの奥までスッキリさせてくれますよ!
チャック付きのパッケージなので、手軽に食べる事が出来ます。
カロリーは、1粒当たり12.8kcalになります。
こちらも、食品に分類されるのど飴となっております。
ミルクのほんのりした味わいとなっているのど飴で、まろやかでとても美味しいのど飴となっております。
13種類のハーブエキスが配合されているので、のどもスッキリさせてくれます。
またアソートなので、いろいろな味が入っているのも嬉しいですよね。
青りんご・オレンジ・グレープ・ピーチの4種類の味が詰込まれています。
1kgといった大容量タイプではありますが、個包装になっているのでいろいろな人に渡しやすいといったメリットはあります。
カロリーは、100gあたり403kcalとなっています。
清涼感を維持するための工夫がされている、巨峰・マスカットといった2種類の味を楽しめるのど飴です。
濃厚な巨峰味・爽やかなマスカット味の飴に、スッキリとしたミント味がブレンドされています。
のどに優しい成分、ミント・ポリフェノールも配合されています。
個包装タイプなので持ち運びも便利!
カロリーは、1粒当たり巨峰味が14.5kcal・マスカット味が14.4kcalとなっています。
ビタミンCが含まれているこちらののど飴は、食品に分類されます。
バヤリースと言えば、ジュースを思い浮かべる方も多いでしょう。
そのジュースの果汁感・なめらかな食感が特徴ののど飴となっています。
オレンジ&マンゴー・赤りんご&青りんご・ぶどう&ピーチといった、2種類の味が1粒になったアソートタイプとなっています。
21種類のハーブエキスも配合されているのど飴です。
カロリーは、1粒当たり16kcalとなっています。
CMなどでおなじみの、チャック付きタイプののど飴となっています。
のどの専門メーカーが開発したのど飴となります。
厳選されたハーブエキスを配合しているのど飴なのですが、それだけではありません。
ハーブを丸ごと使用したハーブパウダーも加えられている、のど飴となっています。
それらが練り込まれているため、味・香りの長続きを実現。
のどの乾燥や、のどを使いすぎたと思った時におすすめののど飴です。
リフレッシュしたい時にも、最適なのど飴となっています。
カロリーは、1袋あたり342kcalとなります。
グレードの高いマヌカハニー(ニュージーランド産)を使ったのど飴となります。
素材の味を生かしたまろやかなタイプののど飴で、10粒入りとなっています。
「少ない」と思うかもしれませんが、試しやすいといったメリットはあるのではないでしょうか?
個包装もされているので、持ち運びも便利です。
カロリーは、1袋あたり127kcalとなります。
のど・鼻を抜ける爽快感を、ぜひ試していただきたいのど飴となっています。
メントールの刺激が強めなので、爽快感を得られる事間違いなしです。
この飴の種類はスーパーメントールだけではなく、フルーツ・和漢びわ・ミルクといった種類も選ぶ事が出来ます。
メントールがちょっとという方にとっては、他のフルーツ味やミルク味があるというのはなかなかのメリットではないでしょうか。
ノンシュガータイプの飴なので、カロリーも抑えめとなっており、1粒当たり9.8kcalとなっています。
ミント本来のすっきりとした味わいを楽しめる、ユーハ味覚糖ののど飴。
着色料などは使っていないので、飴粒自体も透き通った色味となっています。
ペパーミントやハッカ油が配合されていますので、のどの奥まで爽快感が届きます。
優しい甘さなので、リラックスしたい時に舐めるのがおすすめののど飴です。
カロリーは、1粒当たり13kcalとなります。
ビタミンCが140mgも入っているのど飴ですが、140mgというのは1粒当たりに入っている量となっています。
1袋で換算すると、レモン約150個分が入っているという事になります。
ノンシュガータイプののど飴で、12種類のハーブも配合されています。
個包装タイプなので、持ち運びにも困りません。
カロリーは、1粒当たり8.7kcalとなります。
余談ですが…私自身、のどに違和感がある時に購入するのど飴がVC-3000のど飴です。
甘すぎないので美味しく食べられる飴です。
画像ではスティックタイプののど飴となっていますが、袋タイプのものもあります。
こちらの飴は、紀州梅を漬け込んだ特製の梅はちみつを利用したのど飴となっています。
梅の酸味・はちみつの甘さがマッチしており、美味しいという声も多いのど飴で、リピーターも多いそうです。
梅肉エキスと29種類のハーブエキスがのどを優しく癒してくれます。
さっぱりとした梅の酸味・しつこすぎないはちみつの甘さのおかげで、飽きる事なく食べる事が出来ますよ。
カロリーは、1粒当たり13.1kcalとなります。
国立音楽大学声楽家の教授と共同開発して作られたこちらののど飴。
プロポリスを配合しており、のどの痛みの予防も出来ちゃうのです。
歌手などを目指している生徒の声を基に作られた飴でもあり、普段から声を出す事が多い人ほど効果を実感出来るのど飴となっています。
プロポリスというのは、風邪やのどの痛みにも効果的と言われており、症状の緩和以外にも抗菌作用によって予防へと導いてくれる働きがあるのです。
味わいもスッキリしているのは、メントールのおかげ。
気分転換にも最適なので、リフレッシュしたい時に舐めるのがおすすめです!
普段から声を使う事が多い・大声を出す機会が多いという方には、ぜひ選んでいただきたいのど飴です。
カロリーは、1粒あたり12.9kcalとなります。
はちみつきんかんのど飴と聞くと、CMでおなじみのフレーズが頭に流れますが、こちらもおすすめののど飴となります。
のどの痛みや咳に効果が高いと言われているはちみつと、きんかんが使われたのど飴となっています。
はちみつには、殺菌作用以外にも保湿効果にも役立つ食材です。
そのおかげで、痛みを抑えつつ乾燥による悪化も防いでくれる役割を果たしてくれるのです。
一方のきんかんの役割としましては、きんかんにはビタミンCがたっぷりと含まれています。
ですので、風邪予防にも効果があると言えるでしょう。
のどの改善・風邪予防にも繋がるこちらののど飴ですが、はちみつの甘さが苦手という方でも、きんかんのおかげでさっぱりとした後味に!
甘すぎるのが苦手という方でも美味しくいただけるのど飴となっています。
画像はスティックタイプとなっておりますが、袋タイプの物もありますよ。
カロリーは、1粒あたり3.8kcalとなります。
しょうがが含まれているのど飴となっており、しょうがの殺菌作用の働きによってのどの痛み・イガイガといった悩みを解消してくれます。
しょうが以外にも、はちみつ・ゆず・きんかんといった物も使用されているので、それらがしょうがの働きをサポートしてくれる役割を果たしています。
しょうが=体を温めるといったイメージをお持ちの方も多いでしょう。
ですので、のど飴を温かいお湯に入れて紅茶代わりにして飲むのもおすすめです!
冷え対策にもなりますので、1度試してみてもいいのでは?
カロリーは、1袋当たり391kcalとなっています。
のど飴の正しい食べ方

次にのど飴の正しい食べ方についてお伝えします。
医薬品・医薬部外品に分類されるのど飴は、1回目が食べ終わったら2時間以上の間隔をあける必要があります。
早く効果を得たいからという理由で、立て続けに食べ続けるのは良くありません。
やはりカロリーや糖質なども関わってくるので、食べ過ぎないように気をつけましょう。
飴だからとは思わず、普通の錠剤や粉薬と同じように量などを守って舐めるようにしてください。
食品に分類されるのど飴も、食べ過ぎてはいけないという事をお忘れなく。
のどの症状に合ったものを選ぶのも大事です。
効果や効能などをきちんとチェックしてから選ぶようにしてください。
何度も言いますように、食品に分類されるのど飴は効果が期待出来ないので、効果などを求めるのであれば医薬品・医薬部外品を選びましょう。
のど飴の注意点

のど飴に関する、注意点をご紹介します。
のど飴を何個も舐め続ける事は、かえって逆効果に繋がります。
なぜ逆効果になるのか?
それは、せん毛の働きが悪くなるからです。
せん毛の働きが悪くなる=体外から入ってきたウイルスなどの排除が難しくなる可能性が高くなってしまうのです。
さらに、医薬品・医薬部外品に該当するのど飴を舐め続ける事で、有効成分が大いに働いてしまって粘膜を痛めてしまう可能性も0ではありません。
のど飴は砂糖なども多く使われているので、虫歯の原因や糖分の過剰摂取にも繋がってしまいますので、注意しましょう。
妊婦さんも注意が必要!
妊婦さんというのは、いろいろな制限がかかってきます。
のど飴を選ぶ際は、パッケージなどに書かれている成分などをよく見て購入を検討するようにしましょう。
医薬品に該当するのど飴は、体に影響を及ぼす可能性もありますので、妊婦さんだけでなく授乳中のママさんも気をつけるようにしましょう。
食品に該当するのど飴の場合は、体への影響はあまりないと言えますが、アレルギーなどを発症する場合もありますので、気をつけましょう。
まとめ

- のど飴には、潤いを与えたり・痛みを和らげるといった効果がある
- のど飴には、医薬品・医薬部外品・食品といった種類に分けられる
- のど飴を立て続けに舐め続けるのはNGである
という事で今回は、のど飴についていろいろとお伝えしてきました。
【のど飴】と言っても、種類があるというのは初耳で驚きましたね。
選び方のポイントもいくつかご紹介しましたので、ぜひ購入する際は参考にしていただけると幸いです。
なお、食べる際はパッケージの確認を忘れないようにしましょうね!